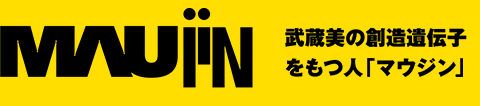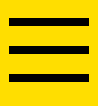常識を超え映画美術の本質に出会う
種田陽平 美術監督

2009年、『ヴィヨンの妻~桜桃とタンポポ~』で第33回日本アカデミー賞・最優秀美術賞を受賞、『THE有頂天ホテル』『フラガール』『悪人』など、さまざまな話題作に携わり、日本を代表する美術監督の一人となった種田陽平。映画美術との出会いは学生時代、絵画助手として制作現場に入ったアルバイトだったが、当時は、映画美術の仕事をやりたいとは思っていなかったという。
Profile
- 種田陽平(たねだ・ようへい)
-
 武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業。美術監督。1986年、石井聰互監督『ノイバウテン:半分人間』で美術監督となる。主な美術監督作品に『スワロウテイル』『キル・ビル Vol.1』『THE 有頂天ホテル』『フラガール』『ヴィヨンの妻~桜桃とタンポポ~』『悪人』などがある。その他CM、舞台美術など幅広い分野で活躍。展覧会『借りぐらしのアリエッティ×種田陽平展』が2010年東京都現代美術館、2011年愛媛県美術館を終え、7月23日より兵庫県立美術館、11月3日より新潟県立近代美術館で開催される。
武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業。美術監督。1986年、石井聰互監督『ノイバウテン:半分人間』で美術監督となる。主な美術監督作品に『スワロウテイル』『キル・ビル Vol.1』『THE 有頂天ホテル』『フラガール』『ヴィヨンの妻~桜桃とタンポポ~』『悪人』などがある。その他CM、舞台美術など幅広い分野で活躍。展覧会『借りぐらしのアリエッティ×種田陽平展』が2010年東京都現代美術館、2011年愛媛県美術館を終え、7月23日より兵庫県立美術館、11月3日より新潟県立近代美術館で開催される。
美術大学のイメージが変わった変革期
わたしが子どもだった頃は、日本の映画界に勢いがあるとはいえず、才能のある映画監督が比較的出にくい時期だったと思っています。ようやく新しい才能をもった新人監督が出始めてきたのは、高校生の頃だったかな。少しずつですが確実に、日本映画界に希望が見え始めているように感じました。ちょうどこの頃、美術大学へ進学することを決め、アトリエに通っていたのですが、美術大学の雰囲気が変わりはじめたのもこの頃だと思っています。
例えば、ムサビ出身の村上龍さん。わたしがムサビに入学した年、村上龍さんの『限りなく透明に近いブルー』が映画化されました。美大生が芥川賞を受賞したり映画を撮ったりと、美術大学に対するイメージが変わりはじめる1つのきっかけだったと思うんです。美術大学は単純に美術のことを突き詰めていくだけではなく、それを超えた次元の可能性やメディアといったものに出会えるんじゃないかという期待感にあふれていた時代だったのではないでしょうか。

そんな状況のなか、わたしが映画美術の世界に出会ったのは大学2年の頃、寺山修司監督の制作現場で絵画助手のアルバイトをしていたときです。しかし、この時点では映画美術の世界に進もうとは思っていませんでした。美術監督というのは、台本や原作を読んでイメージし、そこから設計・建築、ゼネコンへの発注、安全の確保、インテリア選びなど、やらなければならない仕事が山ほどあります。現場で見ていると面倒なことがいっぱいあったし、本当に大変そうでした。わたしは絵を描くことが仕事だったので気楽にやっていましたが、美術スタッフたちの働く姿を見ていると、とても憧れなんて感情はもてませんでしたね。
美術の魅力に気付かせてくれた映画監督たち
結局、わたしは映画美術の世界に入っていくわけですが、最初は仕事に対してそれほど熱意を持てずにいました。それを変えてくれたのは映画監督たちですね。才能にあふれた多くの監督たちと出会ったことが大きなきっかけだと思っています。例えば周防正行監督や、石井聰亙監督。出会った頃はお互いにまだ20代で、「一緒にこんな映画を作ろうぜ」なんて話をしていました。同世代の監督だけではなく、長谷川和彦監督や相米慎二監督、いろいろな世代の監督との出会いが、映画のなかでの美術の重要性、おもしろさに気付かせてくれました。